乾徳山(けんとくさん)、日本の二百名山の一つとしてその名を馳せるこの山は、山梨県山梨市に位置し、標高2,031mの威厳ある姿を見せています。奥秩父山域に属し、JR中央本線塩山・山梨市間から北に望むと、奥秩父の前衛として特徴的な山容を誇っています。
この山の歴史は深く、1330年(元徳2年)に夢窓国師によって開山された塩山の恵林寺があります。国師はこの山で夏の間座禅を組み、修行を行ったとされています。その名の由来は、恵林寺の位置する「乾(いぬい)」方位(易学で北西を意味する)と、徳和村にあることから名付けられたと言われています。
乾徳山の魅力はただ高いだけでなく、山頂直下の国師ヶ原には開拓牧場が広がり、明るい草原の景色を楽しめます。初夏には、山の中腹にある「国師ヶ原」で美しいレンゲツツジが咲き乱れ、その風景は訪れる人々を魅了します。
山頂からの眺めは圧巻で、「1点360度の展望」と呼ばれるように、360度のパノラマが楽しめます。富士山や南アルプス、奥秩父の山々など、壮大な景色が広がるこの場所は、登山愛好家にとっては必見です。
しかし、この山は単なる美しさだけではなく、挑戦も提供します。森林、草原、そして岩峰という三つの異なる地形を体験でき、特にほぼ垂直の岩壁を登る箇所があり、初心者には少々手強いです。山頂付近には鎖場も多く、技術と経験を要する登山が楽しめます。
乾徳山について
場所
山梨県山梨市三富上釜口
標高・百名山・高さランキング
| 山名 | 百名山 | 標高/m | 順位 |
|---|---|---|---|
| 乾徳山 | 山梨百名山 | 2,031 | 349 |
登山口・経由地の標高
| 扇平 | 1,765m |
| 国師ヶ原 | 1,570m |
| 乾徳山登山口 | 988m |
特徴
- JR塩山駅から乾徳山登山口までのアクセスはよい(バスの本数は比較的多い)。
- 岩場が多く、急な鎖場が多い(危険箇所あり)。
- 山頂は比較的狭い。
- 登山コースはバラエティに富んでいる。
- JR塩山駅周辺にはコンビニはないが駅中の売店で軽食は購入可能。
アクセス
行き
JR新宿駅から乾徳山登山口へ
日程とコースタイム
2015.9.12
乾徳山登山口から乾徳山山頂へ
| 出発 9:30 | 乾徳山登山口 AM9時30分着 | |
| 9:45 | 銀晶水 | |
| 10:20 | 錦晶水 | |
| 10:30 | 国師ヶ原 | |
| 10:35 | 高原ヒュッテ(避難小屋) | |
| 10:50 | 月見岩 | |
| 10:55 | 扇平 | |
| 11:40 | 乾徳山山頂 昼食 12:10下山 | |
| 13:20 | 高原ヒュッテ(避難小屋) | |
| 到着 14:20 | 乾徳山登山口 Total時間:約5時間 歩行距離:約6.7km |
気象情報
| 場所 | 天気 | 気温 |
|---|---|---|
| 乾徳山登山口 | 晴れ時々曇り | 18度 |
| 乾徳山山頂 | 晴れ時々曇り | 15度 |
持ち物
今回使用した持ち物は以下です。
山行記録
乾徳山登山口バス停

JR塩山駅からAM8:30発の西沢渓谷行きのバスに乗り、AM9:00に乾徳山登山口バス停に到着しました。

登山口へ向かって進みます。

山道の入り口までは30分程かかるようです。
乾徳山登山口

AM9:30 緑に囲まれた登山口が旅の始まりを告げていますね。足元には小石が散らばり、冒険への期待感を高めます。乾徳山への道標がそこに立ち、山頂への道を静かに示しています。歩を進めるごとに自然の息吹が感じられるでしょう。

15分程で銀晶水に到着しました。

このあたりの斜面はまださほどきつくないです。


突然鹿があらわれました。丹沢の鹿は人を警戒していない様子でしたが、こちらはかなり警戒心が強そうです。

乾徳山の頂上が見えてきました。
国師ヶ原

あと1:45分との事です。まだまだですね。

乾徳山には山頂付近に厳しい鎖場があるそうです。これからが本番でしょう。
月見岩

AM10:50 荘厳な岩肌が目の前に立ちはだかり、月見岩という名前の由来を想像させます。岩の質感とその迫力は、自然が長い年月をかけて作り出したアートのよう。道標に従って進むと、きっと月夜に照らされるこの岩の幻想的な姿を目にすることができるのでしょう。

雄大な自然の中、富士山の頭が遠く中央にちょこんと顔を出しているのが見えますね。空は広く、雲が山のラインを優しく包み込んでいるかのよう。木々の間から見えるその姿は、登山のご褒美とも言えるでしょう。この瞬間のために、多くのハイカーが足を運ぶのだと思います。

冬場などはかなり迫力がありそうですね。
扇平

扇平周辺の開けた風景が、ハイキングの息抜きにぴったりですね。ここからの眺めは、山々が重なり合う美しいパノラマを作り出しています。時には、普段の忙しさを忘れて大自然の中で深呼吸するのもいいものです。ハイカーたちが小さく映るのが、この広大な自然のスケールを物語っています。視界が広がると心もふっと軽くなりますよね。





扇平を抜けると本格的に傾斜がきつくなり、鎖場も現れるようです。

髭剃岩と呼ばれるこの場所は、その名の通り、岩が割れた独特の隙間が特徴です。ここはまるで自然が作り出したアートのような場所で、その隙間に入っていく人たちの姿が、何とも言えない探究心をかき立てます。自然との一体感を感じられる、ちょっと変わったスポットですよね。そこに立ってみると、自然の力と時間の経過を身をもって感じることができるでしょう。

目の前に広がる鎖場は、登山のハイライトの一つと言えるでしょう。岩肌を手で感じながら、一歩一歩慎重に登る瞬間は、まさに冒険心をくすぐります。鎖にしっかりと手をかけ、足元に意識を集中させれば、思いのほかスムーズに進めるものです。ここを乗り越えた時の達成感は、格別なものがありますよ。周りには注意しながら、でも楽しみながら、自分のペースで登りましょう。山頂への道は、まだまだ続いています。

AM11:30 かなり登ってきました。頂上も近いです。


金峰山、大菩薩嶺、富士山などよく見えるはずですが、ガスっているためよく分かりません。


「胎内」と名付けられたこの場所は、神秘的な雰囲気を放っています。岩が自然に形成した空間は、何とも言えない安らぎを提供してくれるかのよう。ここを通るとき、一種のリセットを経験し、新たな気持ちで山行を続けられそうです。

これを登ると頂上ですが、最難関です。

山頂を目前に控えた鎖場は、登山の中でも特に心躍るチャレンジのひとつです。ここでは自分の技術と体力を見極めることが大切。もし不安を感じたら、迂回路を選択するのも賢明な判断。山は無理をせず、自分のペースで進むことが何よりも重要です。この最後の難所を乗り越えた後には、達成感が待っているはずです。
乾徳山山頂

AM11:40 頂上に到着しました。

山頂からの景色は、晴れた日には金峰山や大菩薩嶺、富士山といった雄大な山々を一望できるはずですが、今は神秘的なガスに包まれています。このガスがかかることで、また違った趣のある景観が楽しめますね。雲の流れと光の変化を眺めていると、時間が経つのを忘れてしまいそう。頂上の空気は澄んでいて、一息つくには最適な場所です。天候は山の魅力を左右する大きな要素ですが、こうした変わりやすい天気も登山の醍醐味の一つ。次にここを訪れた時には、また違った景色が待っていることでしょう。



頂上はかなり狭いです。食事の場所を確保するのが大変です。
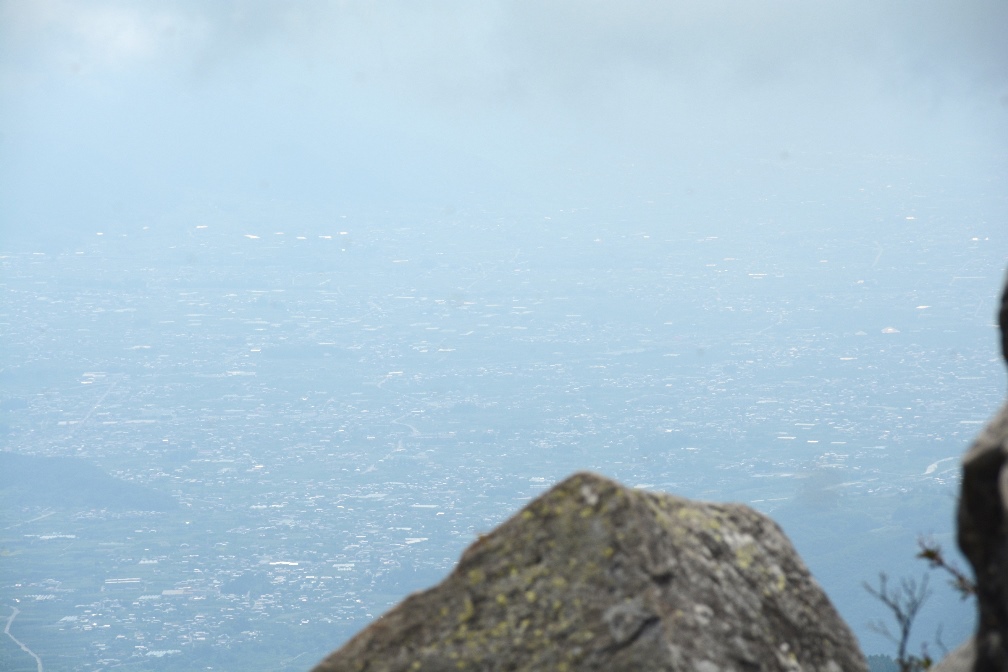
山の頂から見下ろす街並みは、まるで精緻な模型のようです。遠目には建物や道路が小さく整然として見え、日常の喧騒から離れた静寂の中にいることを実感させます。ここからの視点では、人々の暮らしの場が一望に収まり、都市のパッチワークが広がる大パノラマが広がっています。高みからのこの眺望は、登頂の苦労を忘れさせ、新たな視界と感動を提供してくれますね。自然の中で感じる平和と、そこから見る人間界の活気との対比が、なんとも言えない感慨深いものがあります。

下山

PM12:10 食事をとり、下山する事にします。

こちらは息を呑むような断崖絶壁の上からの一枚。足元はしっかりと固めて、一歩一歩慎重に進む必要がありますね。ハイキングシューズがしっかりと岩に接地している様子が、登山の緊張感と興奮を物語っています。深い緑に覆われた谷底を見下ろすと、自然の雄大さと自分の存在の小ささを痛感します。ここでは、安全が最優先。
高原ヒュッテ

高原ヒュッテ、山の中の小さな避難小屋は、ハイカーにとって安心感の象徴ですね。清潔なバイオトイレが完備されているとは、自然環境を大切にする心遣いが感じられます。木々に囲まれたこのヒュッテは、登山の疲れを和らげ、次の行動に備えるための静かな休息地。

PM2:20 麓に戻ってきた景色は、今日一日の旅の終わりを告げています。緑豊かな山々が、登山の思い出を胸に刻む最後のページを飾ってくれているよう。午後3時08分発の塩山駅行きのバスに乗ると、今日の冒険が静かに終わりを迎えます。自然との対話を楽しんだ一日を振り返りながら、心地よい疲れを感じつつ、次の冒険に思いを馳せるのもいいですね。帰宅の途中で見る景色も、また違った美しさがあるはずです。



コメント